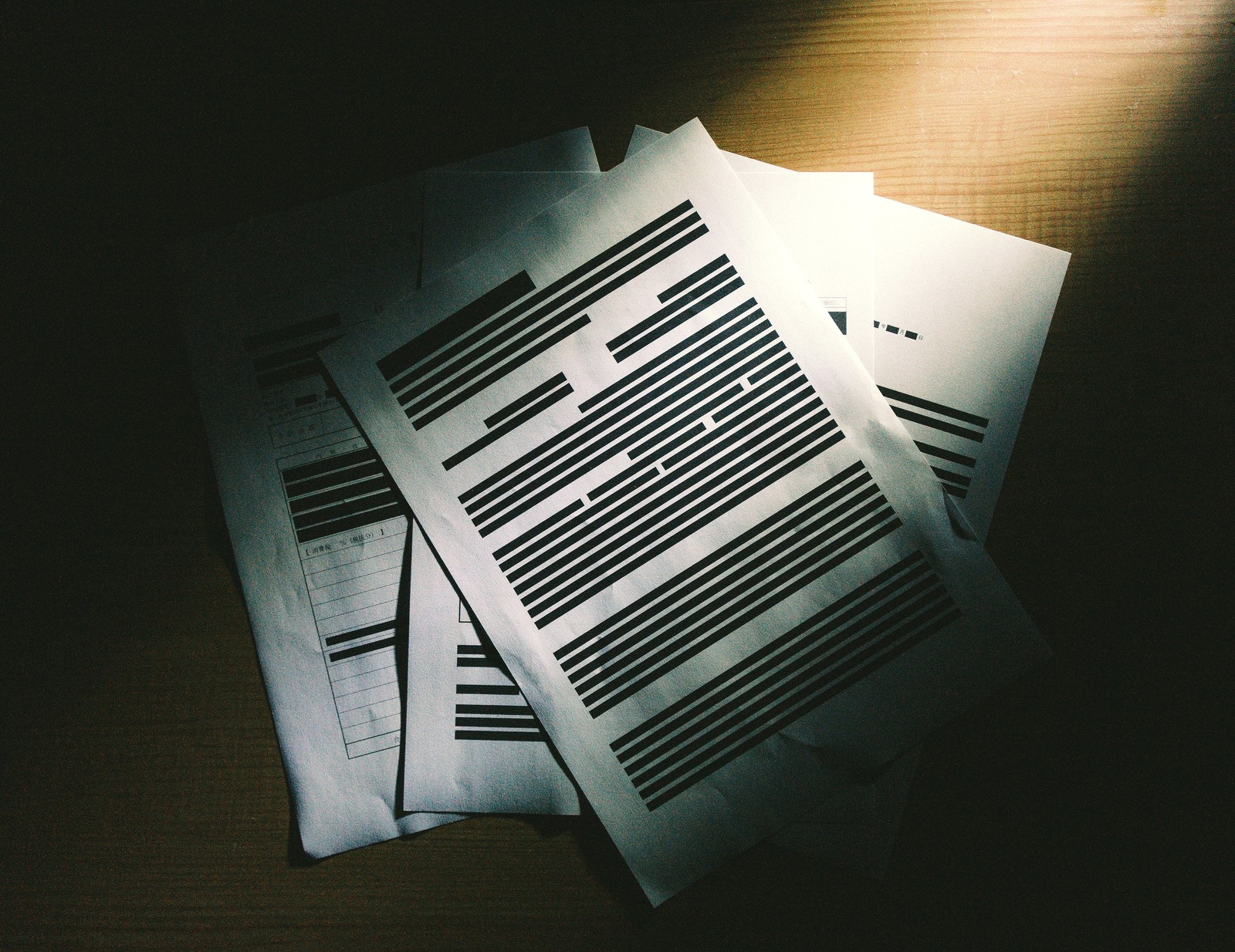
平成30年1月のKPCレポートは、平成29年3月3日の国税不服審判所の裁決事例を紹介していきます。
1 個人が関連法人に不動産を賃貸
不動産貸付業を営む請求人は、自身が所有する「テニスコート及びクラブハウス」の土地・建物(以下「本件物件」という)を年約480万円で関連法人A社に対して貸し付けていました。A社は本件物件を第三者であるB社に転貸して年2,800万円を超える賃貸料を得ていました。なおA社の発行済み株式の総数の全ては、請求人と請求人の子が所有し、請求人の子がA社の代表取締役に就任していました。
2 賃料が固定資産税等の半分以下
請求人は所有及び経営の両面においてA社と特別な関係にあったことから、債務超過であった同法人を支援することとしました。請求人はA社が所有していたクラブハウスの建物を個人で買い取り、従来から所有していたテニスコートの土地と合わせてA社に貸し付ける形態をとりました。しかし年約480万円という家賃は、契約締結当時の本件物件の固定資産税等の額の半分にも満たず、第三者に賃貸する場合の賃貸料の5分の1にも満たない金額だったのです。
3 契約書には「賃貸借契約」と書かれているが、実態は「使用貸借契約」
請求人とA社の間には「テニス施設賃貸借契約書」と題する書面が作成されていますが、実態は対価を得ることを目的としていない「使用貸借契約」であると原処分庁は認定しました。その上で「使用貸借契約」に基づき貸し付けている不動産等に係る固定資産税等や減価償却費は、不動産所得を生ずべき業務について生じたものではないのであるから、不動産所得の計算上必要経費に算入されないとして更正処分をし、国税不服審判所も原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「使用貸借契約」と認定されると、相続税にも大きな影響が
「使用貸借契約」であったと認定されると、相続税にも大きな影響が出ることがあります。例えば土地所有者に相続が発生した場合、借地権や借家権による権利の制約を前提とした「貸宅地」や「貸家建付地」の評価によるのではなく「自用地」の評価によることになります。また「賃貸借契約」であるならば受けられるはずの「小規模宅地等の特例」が受けられなくなることも考えられます。場所によっては相続税が何千万円・何億円も増えてしまうことも十分にあり得るでしょう。
このように「賃貸借契約」か「使用貸借契約」であるかによって、所得税や相続税の額は大きく異なってくることがあります。従来から税務当局との争いになることが非常に多いテーマであることから、典型的な事案と言えます。

