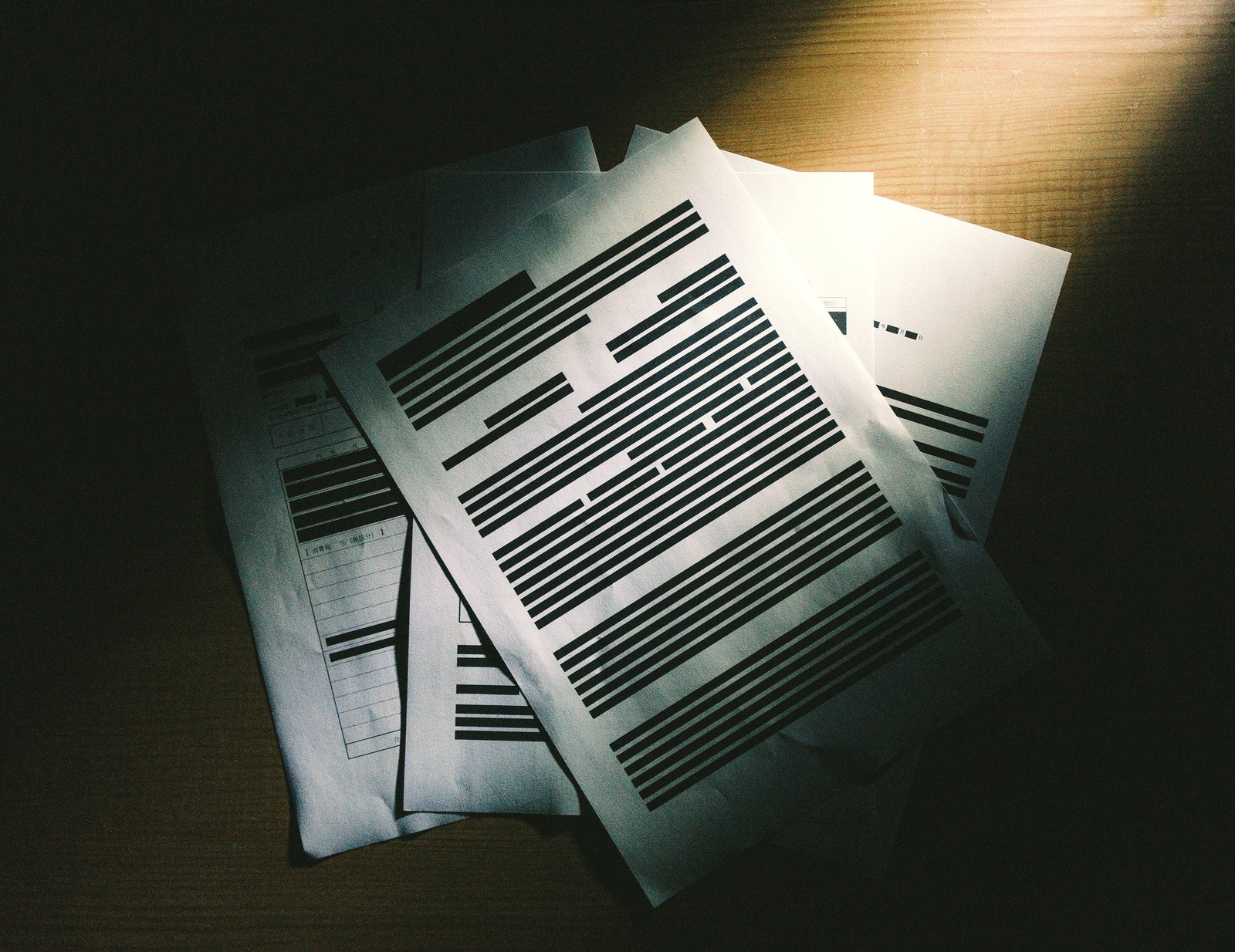
今回のKPCレポートは、司法書士が提案した「民事信託契約」(いわゆる「家族信託」)の一部が公序良俗違反により無効とされた平成30年9月12日付東京地裁判決を紹介していきます。非常に重要な事案であるため、今月と来月との2回に分けて紹介していきます。
1 セミナー・著書等で「家族信託の専門家」として著名な司法書士Bに相談
不動産オーナーであるA氏は、平成27年1月25日、激しい腰痛のため緊急入院しました。検査等の結果、医師より末期の胃がんであり、余命数日と伝えられました。なおA氏の法定相続人は長男、二女、二男の3人でした。父親の死期を察知した二女は、セミナー・著書等で「家族信託の専門家」として著名な司法書士Bに相談しました。Bは平成27年2月1日にA氏の病室を訪れました。
2 全財産を二女と二男に死因贈与
この時、Bは「死因贈与契約書」を持参しており、A氏と二女、二男の3人はその場で署名しました。しかしこの「死因贈与契約書」の内容には大きな問題がありました。A氏の全財産の3分の1を二女に、3分の2を二男に死因贈与するという内容だったのです。つまり長男はA氏の財産を全く相続できないということですから、このままA氏が死去すれば二女及び二男と、長男との間にトラブルが起きる可能性は極めて高いということになります。
A氏は言われるがまま署名してしまった「死因贈与契約書」の危険性に気付いたのか、その翌日の平成27年2月2日、以前から相続の相談をしていた信託銀行を病室に呼んで相談しました。しかし信託銀行の提案は判決文によると「各相続人の法定相続割合を示しているものにすぎず、また、遺言公正証書の案も、どの不動産を誰に取得させるかを具体的に定めず、単に各相続人に法定相続分である3分の1ずつ権利を取得させる旨が記載されており、遺言として特段の意味をなさないもの」に過ぎませんでした。A氏は信託銀行に失望したのか、同日にも病室を訪れた司法書士Bが提案する方法により自身の死後の財産の処遇を決めることにしました。
3 今度は「民事信託契約書」に署名
そして信託銀行が来た3日後の平成27年2月5日、司法書士Bは「民事信託契約書」を持参し再び病室を訪れました。この「民事信託契約書」の内容は、大まかに言うと以下のとおりでした。
(1)信託の目的財産はA氏所有の「全ての不動産及び300万円」とする。
(2)「受託者」は二男とする。二男が死亡等により「受託者」としての任務を果たすことができない場合、二男の長男(A氏から見ると孫)を「新受託者」にする。
(3)本件信託の「当初受益者」は、A氏とする。
(4)A氏死亡後の「受益者」は長男、二女及び二男とし、その割合は長男が6分の1、二女が6分の1、二男が6分の4とする。
(5)「受益者」が複数となった場合は「受益者」の一人は他の「受益者」に対して当該「受益者」の有する「受益権」持分の一部若しくは全部の取得を請求することができる。なお、取得する受益権の価格は、(不動産については)最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする。
(6)受益権を有する者が死亡した場合には、その者の有する受益権は消滅し、二男の子供らが均等に取得する。
A氏と二男は、この日、この「民事信託契約書」に署名をしました。そしてA氏は署名した約2週間後の平成27年2月18日に帰らぬ人となりました。
4 結局のところ、A氏の相続財産を誰がどのくらいもらえるのか
本件は「死因贈与契約」と「民事信託契約」と2つの契約が存在し、かつ「信託」の専門用語が含まれていて非常にわかりにくいと思われるので、平易な言葉に置き換えて少し整理していきます。
まず「信託」の専門用語ですが「受託者」とは「管理者」のようなものだと思ってください。
一方で「受益者」は信託された不動産の「売却代金、賃料等、信託された財産より発生する経済的利益」を受け取ることができます。つまり信託された不動産等の管理は二男に委ねられている一方で、そこから得られる様々な経済的利益については長男、二女及び二男で分けられ、その割合は長男と二女がそれぞれ6分の1、二男は6分の4の割合になると考えてください。
税務上はこの「受益者」が「実質的な所有者」、「受益者としての権利」である「受益権」が「実質的な所有権」として扱われています。判決文でも、この「受益権」が遺留分減殺請求の対象とされており、裁判官もこの「受益権」を「実質的な所有権」と考えていることがわかります。従って皆さんは「受益者」が「実質的な所有者」、「受益権」が「実質的な所有権」とイメージしてください。
これらも踏まえて、結局のところA氏が死去した場合、その相続財産は長男、二女、二男に実質的に以下のようにわけられると整理できます。
(1)信託された「不動産全て+300万円」は「民事信託契約」により「長男6分の1、二女6分の1、二男6分の4」の割合でわけられる。
(2)(1)以外は「死因贈与契約」により「二女が3分の1、二男が3分の2」の割合でわけられる。
このように考えると、長男は信託された「不動産全て+300万円」ついては「遺留分(6分の1)」を何とか確保しているものの、「それ以外」についてはゼロとなっていることから、トータルで見ると遺留分を侵害されていると考えられるということになります。しかも「民事信託契約」では、長男が死亡した場合、その「受益権」は(長男の意思にかかわらず)二男の子供らが相続するという「後継ぎ遺贈型信託」となっていることも大きな問題です。つまり長男は自身が死亡した場合、A氏からもらった「受益権」すなわち「実質的な所有権」を自身の子に相続させることができず、二男の子らに渡さなくてはならないという内容だったのです。
このように基本的にこの「死因贈与契約」と「民事信託契約」は、二女と二男の意向に沿って長男を排斥することを目的としていると判断されても仕方のない内容だったのです。しかもこれだけではありません。この「民事信託契約」には他にも大きな問題点があったのです。このもう1つの問題点が本件を巡る訴訟に極めて大きな影響を与えこととなったわけですが、こちらについては平成31年3月のKPCレポートにて解説します。

