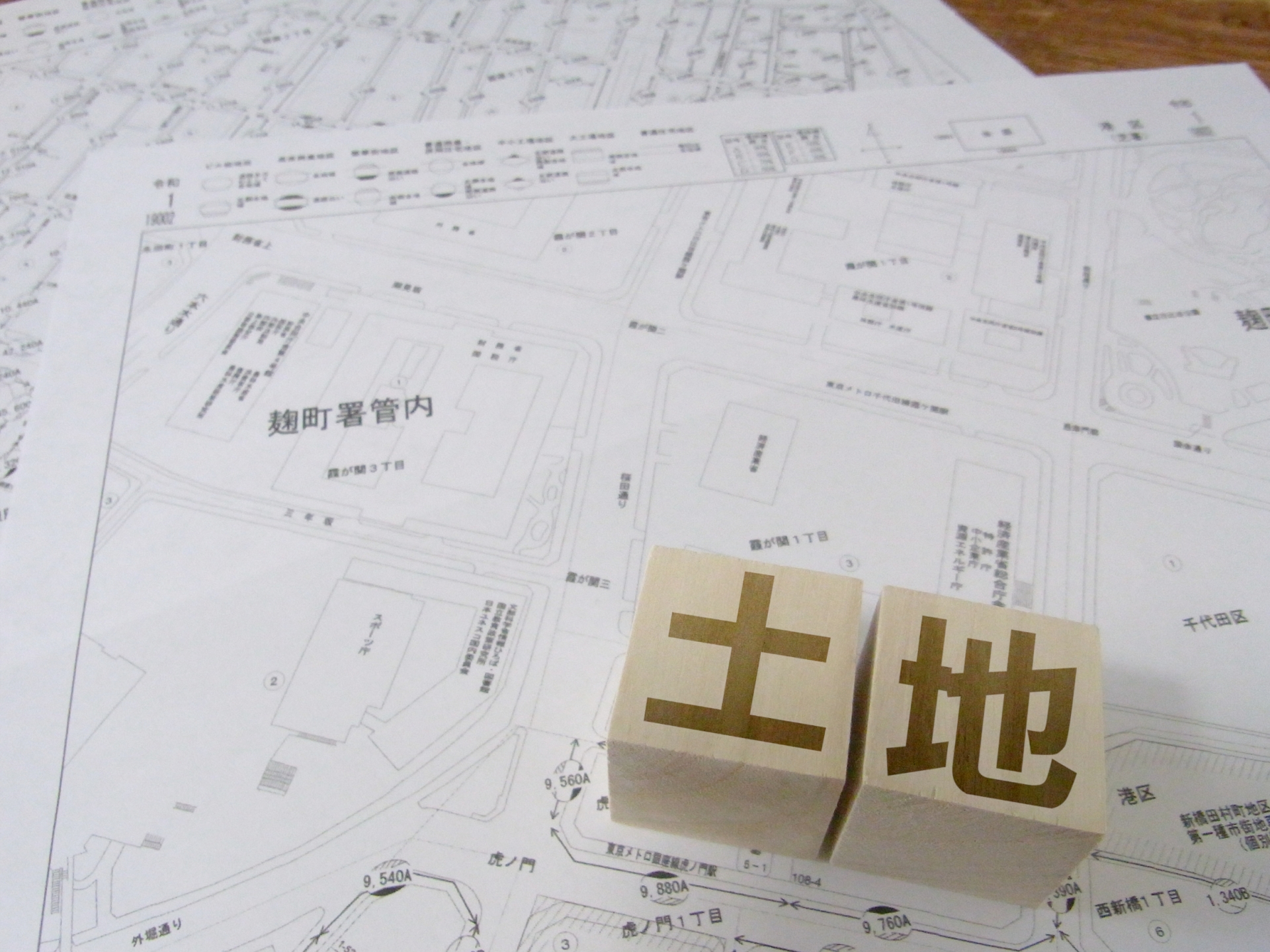
令和2年9月のKPCレポートは「無償返還届出書」が提出されている土地についての「遺留分」の計算について争われた平成31年3月19日東京地裁判決を紹介していきます。
1 概要
平成22年1月6日に死亡したXの法定相続人は、長女、長男、亡二女の代襲相続人である孫、三女、二男、四女,五女、平成18年10月26日に養子縁組を行った二男の妻の8名であり,法定相続分は各8分の1でした。
Xは公正証書遺言を書いており、全ての不動産を含む資産の大部分を二男に相続させるという内容でした。これに対して、長女、長男及び三女の3人が、Xの遺言が遺留分を侵害しているとして、平成22年12月28日、二男に対し、内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をしました。なお三女は平成26年1月13日に死亡したため、本件訴訟の原告は長男、長女、及び三女の長女と次女(Xから見るとこの2人は孫)の4名となり、二男が被告となりました。
2 相続財産の中に「無償返還届出書」が提出されている土地が存在
Xは複数の不動産を有していましたが、遺留分の計算に当たり、その中の甲土地の評価額を巡って原告と被告で大きな隔たりが生じました。甲土地は4,000㎡を超える大規模な土地であり、その上に2棟の建物が存在していました。原告側は「遺留分」を計算する基礎にするための甲土地の評価額を5億9,840万円とするべき主張したのに対し、被告側は2億3,943万4,393円とするべき主張しました。土地の評価の方法は様々ですので、やり方によって一定の差が出るのは当然です。しかしだからと言って、双方の主張が2倍以上も乖離するというのもおかしな話です。なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。
実は甲土地上に存する2つの建物は、いずれも二男が代表取締役を勤める資産管理会社の建物で、借地権設定時に権利金の授受が行われず「無償返還届出書」が提出されていたのです。「無償返還届出書」が提出されている土地の「相続税」の計算については、国税庁通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」により、更地の80%の評価額で行うこととなります。このため、原告側は「遺留分」の計算についても甲土地の評価は「相続税」に合わせて更地の80%を基礎とすべきと主張しました。これに対して、被告側は「遺留分」の計算については、甲土地の存する地域の借地権割合は60%なのだから、更地の40%を基礎とすべき主張したのです。その他の評価についての意見の相違等もふまえた結果、双方の主張に2倍以上の乖離が生じてしまったのです。
3 裁判所の判断
これに対して東京地裁は自身が採用した鑑定結果を踏まえて、まず甲土地を「法律的には標準的借地権(借地権割合は60%)の負担のある底地としての性格を有する一方,経済的には使用借権(借地権割合は10%)の負担のある底地としての性格を併せ持っている」としました。その上で原告の主張について「税法上,無償返還届出書が提出されている貸宅地の評価額は自用地としての評価額の100分の80に相当する金額によって評価するので底地権割合を80%とすべきである旨主張するが,これはあくまでも課税上の負担軽減の基準であり,遺産の時価を求める本件にそのまま適用することはできない。」としました。そして自身が採用した鑑定について「本件借地権が成立してから約11年が経過し,権利関係が安定したことも考慮して,権利割合を加重平均し底地権割合を65%((40+90)÷2=65)としたものであり,本件鑑定1が採用した底地権割合について格別不合理な点や恣意的な点があるとは認められない。」ことなどから、鑑定どおり借地権割合を65%として、甲土地の評価を4億2,200万円としました。
4 「無償返還届出書」は「相続税法」の話であって「民法」の話ではない
何となく鑑定評価に身を委ねて、双方の主張を足して2で割った中途半端な判決のように思えますが、いくつか重要な判示もされています。まず「無償返還届出書」が提出されていると、土地の評価が更地の80%となるというのは、あくまでも「相続税法」の話であるということです。「遺留分」というのは「民法」の話ですから、裁判官の言うように「遺産の時価を求める本件にそのまま適用することはできない」というのは当然でしょう。しかしだからと言って、単純に借地権割合に基づき更地の40%とするのも不合理なように思えます。なぜならばそのように考えると、「遺留分」の計算において、あまりにも不公平な結果になるからです。この点について、数値例に基づいて解説していきます。
5 「不動産の法人化」によって「遺留分」の計算に大きな不公平が生じることがある
仮に甲土地の更地としての時価が、借地権設定時と相続発生時で同額の7億円であったとしましょう。16分の1の「遺留分」が認められる長男の甲土地に係る「遺留分」について考えていくと、少なくとも以下の3パターンが考えられます。
(1)パターンA
まずはパターンAとして、借地権設定時にXが甲土地の時価の60%相当の権利金を受領していた場合を検討していきます。言うなれば、これが商慣行にそった最も当たり前のやり方です。甲土地の存する地域の借地権割合が60%ということは、借地権が設定されることによってXが所有する甲土地の評価は更地の概ね40%程度に下がってしまうということを意味します。そういう意味ではXの相続財産は減ってしまいますが、一方でXは甲土地の時価の60%相当の権利金を現預金で受領しますから、所得税等引後の権利金が現預金としてXの手許に残り、その分は相続財産が増えることになります。これらを差し引きするとどうなるかを、まとめたのが以下の数値例です。なお権利金に課税される所得税等の計算に当たっては、取得費は概算取得費、譲渡費用は無いものとし、復興特別所得税などは無視しています。
①Xが受領した権利金
7億円×60%=4億2,000万円
②権利金にかかる所得税等
(4億2,000万円-4億2,000万円×5%)×20%
=7,980万円
③所得税等引後の権利金の残金
4億2,000万-7,980万円=3億4,020万円
④甲土地の相続税評価額
7億円×(1-0.6)=2億8,000万円
⑤長男の遺留分
(3億4,020万円+2億8,000万円)÷16=3,876万2,500円
おわかりいただけましたでしょうか。甲土地に関連する相続財産は、受領した権利金から所得税等を支払った残金に相当する現預金3億4,020万円と、借地権設定によって更地の40%まで時価が低下した甲土地2億8,000万円となるため、長男の「遺留分」はその16分の1の3,876万2,500円となります。
(2)パターンB
パターンBは、借地権設定時に権利金の授受が行われず「遺留分」の計算の基礎となる甲土地の評価は更地の80%とする場合です。これが言うなれば、本件で原告側が主張した考え方です。Xは権利金を受領していませんから現預金はゼロとなり「無償返還届出書」により評価が更地の80%へと低下した甲土地のみが相続財産ということになります。
①甲土地の相続税評価額
7億円×80%=5億6,000万円
②長男の遺留分
5億6,000万円÷16=3,500万円
原告側としては、全力で自身に有利な主張をしたつもりですが、それでもパターンAならば3,876万2,500円の「遺留分」があったのに比べると、やや不利になっているということになります。
(3)パターンC
パターンCは、借地権設定時に権利金の授受が行われず「遺留分」の計算の基礎となる甲土地の評価は更地の40%とされた場合です。これは本件で被告側が主張した方法です。パターンBと同じく現預金はゼロで、甲土地は更地の40%の評価で「遺留分」を考えます。
①甲土地の相続税評価額
7億円×40%=2億8,000万円
②長男の遺留分
2億8,000万円÷16=1,750万円
このようにパターンCだと「遺留分」はパターンAの半分以下ですから、長男はかなり不利になるということになります。
実はこの「建物名義を資産管理会社にし『無償返還届出書』を提出する」というやり方は「不動産の法人化」と称して数多く行われています。もちろん相続人同士の人間関係が良好であれば「遺留分」の計算という議論そのものが起きませんから問題はないでしょう。逆に言うと、相続人同士の人間関係が不安定な家で、税金対策になるなどと言われて安易に「不動産の法人化」をやると後から大きなトラブルになる可能性があるということになります。
6 「税法」と「民法」はまるで異なるロジックで動く
ここは私の推測ですが、裁判官は法律を突き詰めれば「パターンC」によるべきではないかと考えたものの、それではあまりにも不公平な結果になると考えて、やむなく「パターンBとパターンCを足して2で割るような中途半端な判決」を出さざるを得なかったのではないでしょうか。この判例が実務のスタンダードになるかどうかは定かではありませんが、だからと言って民法的には何が正しいのかと聞かれるとハタと困ってしまうような話です。ただ1つ言えることはあくまでも「無償返還届出書」は「税法」の話ですから、それと「民法」の話はまるで別であり「更地の80%」という「税法」の世界のロジックを「民法」の世界にそのまま当てはめることはできないということです。
非上場株式の「事業承継税制」などもそうですが「税務」の話ばかり考えていると「法務」で大きな落とし穴にはまることが考えられます。何かを実行する時は法律専門家にもオピニオンをいれてもらって慎重に検討しましょう。

